未成年後見人を決める手続(親権者が亡くなった後のために)

 |
東京都墨田区、錦糸町駅近くにある鈴木淳也総合法律事務所です。 |
認知してもらった後に自分が死亡したら親権者は認知した男性となってしまうのか?
今は自分が親権者だけど、自分が死んだ後、元配偶者が親権者となってしまうのか?
このようなご相談をいただくことが多々あります。
シングルマザーの方や、離婚後の親権者の方がご自分が亡くなった後にお子様を誰が監護するのか心配されているのです。
結論として、自動的に親権者が変更されることはありません。
しかし、親権者変更の手続をとられて、認められた場合には変更されることになります。
それを回避するためには、その前に未成年後見人が付くことが必要となります。
そこで、未成年後見人が決まる手続等について解説します。
目次
未成年後見人とは
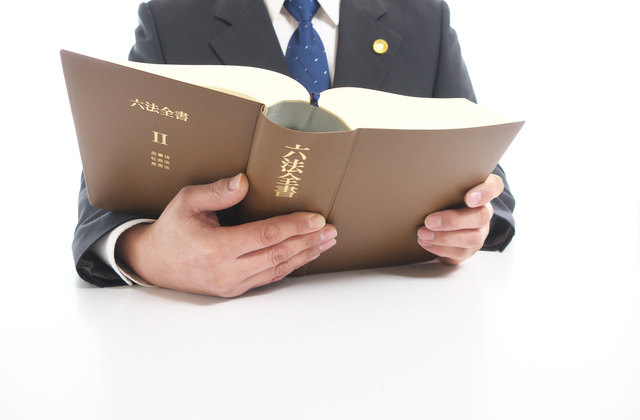
未成年後見人とは、未成年者に対して親権を行う者がいないとき又は親権を行う者が管理権を有しない場合に選任される者のことです。未成年者の身上監護や財産管理を行います(民法838条1号参照)。
未成年後見人となりますと、子に対する監護・教育、居所指定といった民法820条から823条までに規定する事項について、親権者と同一の権利義務を有することになります(民法857条)
どのような場合に未成年後見人を付けるのか

婚姻期間中は共同親権となりますが、未婚の母や離婚後の親権者は単独親権者です。
このような単独親権者が亡くなり、親権者が不在となった場合に未成年後見人を付けることになります。
以下の2通りの方法で未成年後見人が決められます。
①親権者が遺言書で未成年後見人を指定する
②家庭裁判所に申し立てをする
それぞれの方法について以下で解説します。
遺言書で未成年後見人を指定
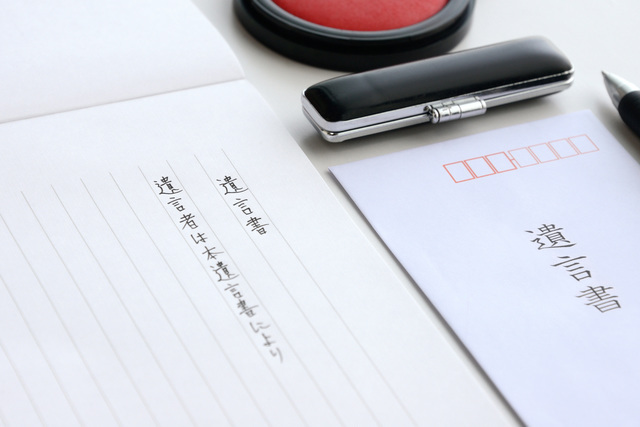
遺言書で未成年後見人を指定することが出来ます。
民法839条
1項 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。
この場合の後見人を指定後見人といいます。
指定後見人は、最後に親権を行う者だけが指定することができます。
⑴遺言書で指定するメリット
①親権者の意思を反映させることが出来る
自分の死後、誰が未成年後見人になるのかが最大の心配事かと思いますが、自分が指定できるというのが一番のメリットといえます。
②手続が簡単
裁判所の手続は必要なく、遺言書を作成してその中で指定し、死後は後見人となる者が役所に後見開始届書を提出すればいいだけです。
⑵遺言書で指定するデメリット
指定後見人の場合は、後見事務について裁判所へ定期方向する必要がありません。
したがって、監視の目がないのをいいことに適切に仕事がなされない可能性もあります。
未成年後見監督人を遺言書で指定することも可能ですので、心配な方は未成年後見監督にも指定しておきましょう。
⑶未成年後見人就任までの流れ
①指定後見人をお願いした人から承諾を得ておく
↓
②未成年後見人を指定する遺言書の作成
↓
③死亡後、必要に応じて遺言書の検認手続
↓
④後見の開始届書を死後10日以内に役所に提出する
検認手続を経る場合は、手続に期間を要するため死後10日以内に開始届書を提出することは困難です。
公正証書遺言であったり、自筆証書遺言の保管制度を利用している場合は、検認手続は必要ありませんので、10日以内に提出するようにしましょう。
家庭裁判所に未成年後見人選任申立ての流れ

申立人となるのは以下の者等です。
・未成年者本人 ※ただし意思能力が必要です
・未成年者の親族
・その他の利害関係人
①申立書を作成して家庭裁判所に提出する
申立人となるのは以下の者等です。
・未成年者本人 ※ただし意思能力が必要です
・未成年者の親族
・その他の利害関係人
申立書には、未成年後見人候補者を記載する欄があります。候補者を具体的に記載せず裁判所に一任することも可能です。
申立人自身を候補者とすることが多いです。
↓
②申立人・候補者・裁判所とで面接し、裁判所が未成年後見人を決定
↓
③審判書が未成年者後見人のもとに届き、未成年後見人就任の効力が発生
↓
④裁判所が未成年者の本籍地の役所に連絡し、未成年者の戸籍に後見人が選任された旨記載される
↓
⑤最初の仕事として、未成年者の資産等を調査し、「財産目録」、「年間収支予定表」を作成し裁判所に提出する
まとめ
・単独親権者が死亡しても自動的に元配偶者が親権者となることはない
・遺言書で未成年後見人を指定しておくと、スムーズに未成年後見人が就任することができる
・公正証書遺言、自筆証書遺言保管制度を利用すればよりスムーズに行うことができる
・未成年後見人を遺言書で指定する場合は、未成年後見監督人も一緒に指定しておくと安心
・家庭裁判所に申立てをして未成年後見人を選任してもらうことが出来る
離婚・男女問題のご相談は当事務所へ

未成年後見人の指定は生前に遺言書によって行うが良いでしょう。
当事務所は、離婚等の男女問題の他、相続案件も多数取り扱っており、遺言書の作成も対応しております。
初回の相談料は無料です。
当事務所では、電話面談も実施しておりますので、遠方の方からもご相談、ご依頼いただいております。
面談は事前予約制です。問い合わせフォームからお問い合わせいただき予約をお取りください。
【関連記事】
・【離婚】親権者とは(判断基準、変更などについて)
・【監護者指定の審判】子供と一緒に暮らすために重要なこと
・【認知・養育費】未婚の母が知っておくべきこと
