【監護者指定の審判】子供と一緒に暮らすために重要なこと

 |
東京都墨田区、錦糸町駅近くにある鈴木淳也総合法律事務所です。 |
別居中である場合、後に親権を獲得するために、監護者であることは重要です。もし貴方が現在お子様と一緒に生活していない場合、そして離婚後の親権を望む場合は、早急に監護者の指定を受ける必要があります。以下で詳しく解説します。
目次
どのような場合に監護者を指定するのか
監護者とは親権の一部である監護権を有する者のことです。子供と一緒に生活をして身の回りの世話をする人のことです。
監護者を指定する場面は、離婚前と離婚後の2パターンあります。
前提にある親権について説明します。
婚姻中は父母の両方に親権が認められる共同親権となっています(民法818条3項)。
しかし、離婚するとなると、どちらか一方だけしか親権者とすることができません。
⑴離婚前の監護者指定
離婚前、すなわち婚姻中は共同親権であるため、父母の両者に親権があります。ただ、父母が別居しているような場合、子を連れ去られた場合に監護者を指定する実益があります。監護者の指定を受けると、他方の親は監護権を行使することが出来なくなるのです。
これによって、配偶者の影響を受けずに、子を監護していくことが可能となります。監護者の指定を受けるためには、家庭裁判所に監護者指定の審判を提起する必要があります。子と一緒に暮らせていない方の親は、監護者の指定を求める審判を提起するのと同時に子の引き渡しを求める審判も提起することになります。
⑵離婚後に監護者指定
離婚時に親権について争いがある場合、親権者を一方の親と定め、監護者を他方の親とすることがあります。
たとえば、父を親権者として、母を監護者とする場合、子は戸籍上は父の戸籍に入ったままですが、母と一緒に生活することとなります。
離婚後、親権者を変更するまではないのだけど、子が一緒に生活する親を非親権者に変更するといった場合に、監護者の指定を行うこととなります。
このように、離婚前と離婚後で監護者の指定をすることがあるのですが、離婚後に監護者を指定するケースは稀であり、離婚前に子の引き渡しを求める場面で監護者の指定を求めることが多いです。
すなわち、 「子の引き渡し」と「子の監護者指定」の審判を同時に家庭裁判所に申し立て、裁判所に監護者を決めてもらうことになるのです。
監護者指定の判断基準
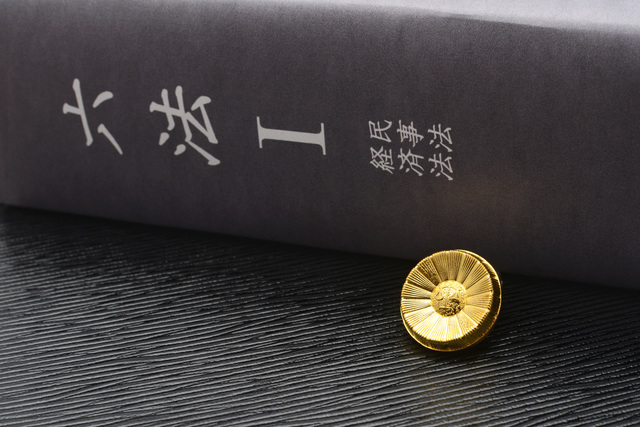
監護者をどうするかの判断というのは、親権者を決める際の判断基準と同じです。
ですから、 別居中に監護者の指定がなさますと、離婚の際の親権者は基本的には監護者と指定された親がそのままなることになります。
親権者・監護者を定める際の判断基準として根底にあるのは、子の利益を最優先に考えるということです。客観的な事情を踏まえて、どちらの親に定めることが子の利益に適うことになるのかを裁判所は考えます。
子の利益を考えるにあたっては、以下のような事項が判断の際の検討材料となります。
・監護の実績、継続性
・監護能力
・面会交流を許容する意思
・子の意思
・きょうだい不分離
それぞれについて、以下で詳しく解説します。
監護の実績・継続性
子にとっては、これまでの生活環境をなるべく変更しないことにこしたことはありません。
子の現状を最大限尊重し、特段の事情のない限りこれまで子が育ってきた生活環境を今後も維持した方がいいという考え方が重要視されます。
そこで、父母がこれまでどれだけの期間、どのようにして監護してきたのかということをふまえ、主たる監護者がどちらなのかが親権者や監護者を決める際の重要な判断基準となります。
監護状況というのは大きく二つの場面に分けられます。
①子が生まれてから別居までの期間
②別居後の期間
①,②ともに一方の親が主に監護してきたという場合には、主たる監護者の判断は問題ないでしょう。
一方で、①と②で主たる監護者が異なる場合、それぞれの期間や子との精神的結びつきがどちらが強いのかといったことをふまえ、主たる監護者がどちらなのかを総合的に判断していくことになります。
子どもの連れ去りはマイナス

一方の親が監護を継続しているのだけど、その監護の開始が子を無理やり連れ戻すといった違法行為によって始まったという場合、そのような違法による監護状況を今後も維持すべきであるという主張はとおりません。
ですから、あなたが現在、子を監護していない場合、子を無理やり連れ戻して自分の生活状況下に置くのではなく、子の引き渡しを求める審判の申立をするなど早急に法的対応を行うべきです。
【札幌高裁平成17年6月3日決定】
事案
妻が夫の浮気を疑い2歳の女児を連れて実家に帰り、別居を開始。夫が妻の実家にやってきて、1日だけ自分の親に会わせたいと主張したため妻が応じた。その後、妻は女児を引き取るために夫に連絡したが、夫が一切拒否したため、監護者の指定と未成年者の引き渡しを求める調停を申し立てた。
判断
抗告人は、未成年の安定した状態、抗告人の実母の協力による監護態勢、抗告人の資力等、子の福祉という観点から、監護者は抗告人が適当であると主張する。しかしながら、相手方の監護権を侵害した違法状態を継続している抗告人が現在の安定した状態を主張することは到底許されるものではない。また、未成年者がいまだ2歳の女児であり、本来母親の監護が望ましい年齢にあることに加え、記録からは、相手方が育児をすることについて不適格な事情が認められない本件では、未成年者の監護者として相手方が相当であることは明白である。
監護能力
監護能力というのは、子を育てる能力のことです。経済力、健康状態などを踏まえて実際に子を育てていけるのかどうか判断されます。
たとえ経済力が十分にあるとしても、子に対して食事を提供できない、子と一緒に遊べない、子を病院に連れて行かず放置する癖があるといった場合は、子の監護能力が劣ると判断されることになります。
面会交流を許容する意思があるか

子の成長のためには、別居親とも良好な関係を築いていくことが重要です。そのため、同居親が別居親との面会交流についてどのような考えがあるのかという点も監護者を決めるにあたり重要な要素となります。
また、離婚する前に別居状況があった場合は、実際に面会交流の実施状況についても考慮されます。
たとえば、離婚前の時点で、一方の親が面会交流の実施に非協力的で日程調整で揉めていたというような場合、「子が親の対立に巻き込まれ両者の板挟みとなって両親に対する忠誠心の葛藤から情緒的な安定を失い、その円満な人格形成及び心身の健全な発達に悪影響を及ぼすことが懸念される」と裁判所は判断しています(東京高裁平成15年1月20日決定)
ただし、暴力癖があるなど別居親に問題があり、子の為を考えると安易に面会交流を許容できないといった特別な事情がある場合には、
同居親が面会交流の実現に消極的であっても影響はないといえるでしょう。
子の意思
親権者や監護者を定めるにあたっては、子の陳述を聴取するなどして子の意思を把握するように努め、子の年齢や発達状況に応じてその意思を考慮されることになります。
家事事件手続法第65条
家庭裁判所は、親子、親権又は未成年後見に関する家事審判その他未成年者である子(未成年被後見人を含む。以下この条において同じ。)がその結果により影響を受ける家事審判の手続においては、子の陳述の聴取、家庭裁判所調査官による調査その他の適切な方法により、子の意思を把握するように努め、審判をするに当たり、子の年齢及び発達の程度に応じて、その意思を考慮しなければならない。
子が10歳前後以上であれば意思を表明する能力に問題がないとされています。子の意思能力に個人差がありますので、小学校低学年の子の意思能力をどうとらえるかは難しいところです。
15歳以上の子
15歳以上の場合は、親権者・監護者を指定するにあたって、子の意思は大きく尊重されることとなり、子の陳述の聴取が必ず行われることとなります。
家事事件手続法第169条
2 家庭裁判所は、親権者の指定又は変更の審判をする場合には、第六十八条の規定により当事者の陳述を聴くほか、子(十五歳以上のものに限る。)の陳述を聴かなければならない。
就学前の幼児
子が別居親に対し拒絶反応を示していても、それを直ちに子の意向として重視されることはありません。
同居親や周囲の影響を受けやすいと考えられるからです。
きょうだいの不分離
子にとっては、兄弟姉妹を切り離さず一緒に生活させる方がいいという考えです。
特に幼児期においては重要性が増すことになります。一方で、子の年齢が高くなるにつれて、重要性は薄れます。
また、兄弟姉妹に関しては、親権を判断するにあたりそこまで重要な要素ではありません。
監護者の指定に関するご相談は当事務所へどうぞ

以上のとおり、監護者を父母のどちらに指定するかを決める判断基準は多岐にわたります。
単に経済力があるから、子への愛情が強いから、といった事情だけで決まるものではありません。
裁判所に対し、自分が監護者として適切であることを判断基準に即してしっかりと説明していく必要があります。
一人では心細いと思われますので、ぜひ弁護士にご依頼なさることをお勧めします。
当事務所では養育費トラブルについて積極的に取り扱っています。
初回の相談料は無料です。
当事務所では、電話面談も実施しておりますので、遠方の方からもご相談、ご依頼いただいております。
面談は事前予約制です。問い合わせフォームからお問い合わせいただき予約をお取りください。
【関連記事】
・【離婚】親権者とは(判断基準、変更などについて)
・子の引き渡しを求める方法【離婚前の別居中に子を連れ戻す】
・【離婚】面会交流とは(調停・審判や拒否する場合の間接強制など)
