【相続】遺言書の種類と作成するメリット
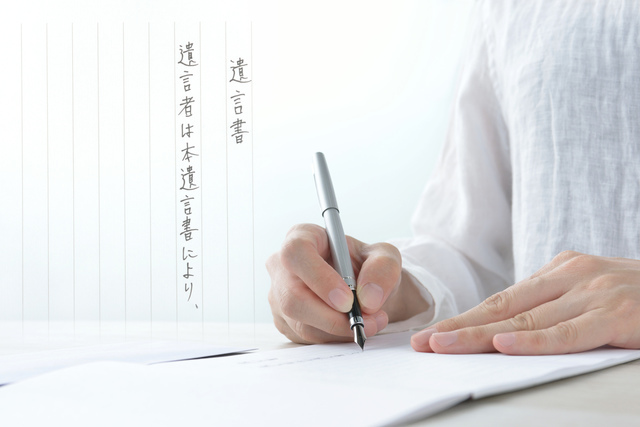
 |
東京都墨田区、錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。 |
遺言とは
遺言は、遺言者の最終的な意思を残す重要な行為です。
最後のメッセージともいえます。
遺言は、遺言者が死亡した後にその効力が生じます。
ですから、相続人が遺言書の内容を遺言者に確認しようと思っても、
それは叶わないわけです。
ですから、後に疑義が生じないように、遺言者の意思が反映された遺言書を作成することが重要となります。
弁護士に作成を任せるのがいいでしょう。
遺言書の種類

遺言書にはいくつか種類がありますが、一般的に多く使われるのが、自筆証書遺言と公正証書遺言になります。
⑴自筆証書遺言
全文を自書で作成する遺言書のことです。ただし、財産目録に関する部分は自筆ではなく、ワープロで入力し出力した者でも構いません。
メリット
①気軽に作成できます。誰もかかわることなく、いつでも思い立った時に作成できるのがいいところです。
②手数料が一切かかりません。
③遺言内容を誰にも知られません。立会人が必要な公正証書遺言は特定の第三者に内容を知られてしまうことになります。
デメリット
①方式が細かく決められているため、違背すると遺言が無効となってしまいます。せっかく作成したのに、自分の意思が死亡後に全く反映されないことになってしまいます。弁護士に作成をお願いするのがいいでしょう。
②作成後に紛失、第三者に改造されるおそれがあります。弁護士に保管を依頼するなど対応が必要です。
③亡くなった後、家庭裁判所の検認手続が必要となる。検認手続には一定期間を要するため、手間となります。
検認手続については、こちら
⑵公正証書遺言
公正証書遺言というのは、公証人によるチェックを経て、公証役場に保管される遺言書です。以下で述べるとおり、公正証書遺言にかかわる人物は、遺言者本人、公証人、2名の証人の計4名となります。
メリット
①公証人が確認して作成するため、方式違背で無効となるリスクがありません。
②第三者に改ざんされるおそれがありません。公証役場にて保管されますので、安心できます。
③亡くなった後、家庭裁判所の検認が不要です。検認手続の手間を省けます。
④自書出来なくても遺言が可能です。
デメリット
①公証役場への手数料がかかります。
②証人が二人必要となります。これによって、証人には遺言書の内容を知られてしまうことになります。
証人は誰でもなれるわけではなく、民法では欠格者が定められています。
第974条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
1未成年者
2推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
3公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
⑶自筆証書遺言保管制度
自筆証書遺言保管制度というのは、自筆証書の遺言ではあるのですが、自分で保管するのではなく、法務局にて保管してもらえる制度のことです。新しく設けられた形です。
自筆証書遺言と公正証書遺言のハイブリッド型のようなものです。
単なる自筆証書遺言には無いメリットは、遺言書を作成した後に紛失したり改ざんされるリスクが無くなることです。相続時の検認手続も必要なくなります。公正証書遺言と比べても、費用が安く済むというメリットがあります。
一方で、あくまで自筆証書遺言ですので、公正証書遺言と異なり専門家のチェックが入りません。そのため、法的に無効である可能性もあります。
一番いい方法は、弁護士に自筆証書遺言の文面の作成を依頼して、自筆で作成した後、自筆証書遺言保管制度を活用することです。
遺言書を作成するメリット

・死後の相続人らの紛争を防止できる
・推定相続人でない者にも財産を渡すことが出来る
・世話をしてくれた相続人に法定相続分以上の財産を渡すことが出来る
・弁護士を遺言執行者に指定し、遺言どおりの財産分配を行うことができる
遺言書がない相続は、揉める可能性が非常に高いです。
財産を残す側としては、このような紛争が起こらないようにしておくことも重要です。
遺言書の作成は当事務所へ

当事務所では遺言書の作成のお手伝いをしております。
遺言執行者もお引き受けしております。
初回は無料相談となります。
電話による相談も可能で、遠方にお住まいの方からの依頼も承っております。
ご相談は事前予約制です。問い合わせフォームからお問い合わせいただき、面談の予約をお取りください。
【関連記事】
