【自己破産】残せる財産(自由財産)残すための方法
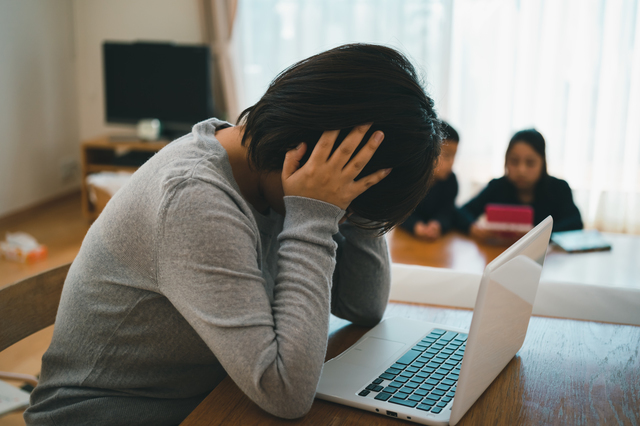
 |
東京都墨田区の錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。 |
自己破産とは、ざっくり言えば、①破産する人の財産を処分、②処分で得られた金銭を債権者へ配当、③それでも残ってしまった債務(借金)をゼロにしてもらえるかどうか裁判所が決める手続のことです。
破産をすると財産が全て処分されてしまう、と考えられている方がいらっしゃいますが、誤解です。
自己破産をしても残せる財産について解説していきます。
目次
自由財産かどうかがポイント

自己破産手続で財産を残せるかどうかのポイントは、自由財産にあたるかどうかです。
自由財産とは、自己破産をしても法律上残すことが許される財産のことです。
自己破産手続によって全ての財産が処分されてしまうとすれば、自己破産する方は今後、生活が出来なくなります。
それはあまりにも不合理です。
自己破産手続というのは、そもそも生活を再建しやり直しをするために法律で認められた手続です。
ですから、一定の範囲内の財産について残せるようになっているのです。
このような理由から、自由財産が定められていますので、法人(会社)が破産する場合は、自由財産というのは存在せず、全ての財産が処分されることになります。会社は、破産すると消滅するわけですから、少なくとも破産という手続を選択する以上、財産を残す必要がないのです。
自由財産の具体例
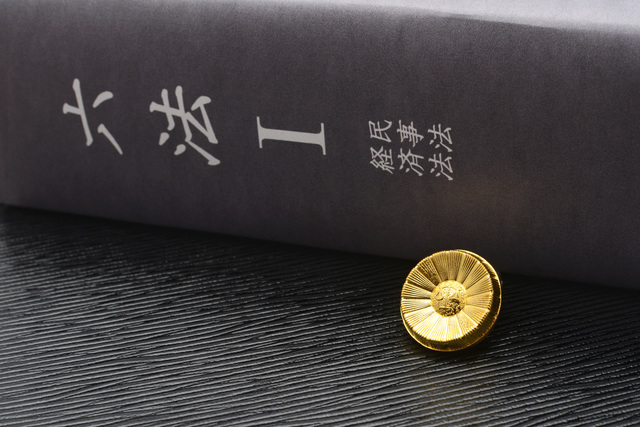
⑴ 新得財産
新得財産というのは、破産手続開始決定後に得た財産のことです。
破産手続で処分される財産の基準となる時点は、申立てをした裁判所が破産手続開始決定を出した日です。開始決定日といいます。
開始決定というのは、「自己破産を申立てた人には支払い能力がないので、破産手続きを進めていきます」という旨の裁判所が行う決定のことです。裁判所に破産の申立(申立書を裁判所に提出)をしてから、早ければ当日、だいたいは1週間から2週間程度で開始決定が出ます。
開始決定より後に得た財産は新得財産ですので、例えば、開始決定後に給料が支給されて預金残高が増えた分については処分されません。
裁判所に自己破産の申立てをしてから、開始決定が出るまでの間に生活費の為に預金を引き出したり、口座引き落としがかかって残高が減っても特に問題はありません。開始決定日の残高を基準に動いていくことになります。
⑵ 差押禁止財産(破産法34条3項2号)
民事執行法という法律では、差押が禁止される財産が定められています。
具体的な一例は以下のとおりです。
☑債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
☑債務者等の1か月間の生活に必要な食料及び燃料
☑標準的な世帯の2か月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭
⑶ 99万円以内の現金(破産法34条3項1号)
99万円までは自由財産として処分されることはありません。
ここで注意すべきは、後述の預貯金とは全く別ものとして扱われます。
手持ち金として所持しているか、依頼した弁護士の預かり金口座に入っていれば、現金として扱われて、維持することが可能となります。
例えば、東京地裁の場合、代理人が過払い金を回収して依頼人口座に返還せずに、代理人が預かっている状況であれば、99万円までは処分されません。
一方で、代理人が依頼人の口座に銀行振り込みの方法で返還し預金残高として残っていると、預貯金として扱われるため、後述する金額を超える場合は処分の対象となってしまいます。
⑷ 破産手続で自由財産の範囲の拡張が認められた財産
上記3つ以外であっても、破産手続の中で自由財産の範囲の拡張が認められた財産については、処分されません。
範囲を拡張するかどうかは、管財人の意向を踏まえ裁判所が決定することとなります。
例えば、公共交通機関が発達しておらず、自動車がどうしても生活に欠かせないという場合に、さほどの価値のない自動車であれば自由財産の範囲の拡張の申立を行い、認められると自由財産として扱われ、処分されずに済みます。
裁判所では、一定の範囲の財産について、予め処分対象としない、すなわち自由財産の拡張を認めるという基準を設けております。
東京地方裁判所では、以下の財産は原則処分されません。
①残高が20万円以下の預貯金
ただし、口座が複数ある場合は、合算して20万円以下である必要があります。
②見込額が20万円以下の生命保険解約返戻金の保険
ただし、保険が複数ある場合は、合算して20万円以下である必要があります。
③処分見込額(評価額)が20万円以下の自動車
④支給見込額の8分の1相当額が20万円以下の退職金債権
⑤支給見込額の8分の1相当額が20万円を超える退職金債権の8分の7相当額
例:支給見込の対象金が240万円である場合、その8分の1は30万円ですので、210万円は処分対象から外れることになります。
⑸ 破産管財人が放棄した財産
財産の買い手が見つからず、破産管財人が裁判所の許可を得て財産を放棄することがあります。
例えば、地方の価値のほとんどない不動産等です。
自由財産とならない財産を維持する方法
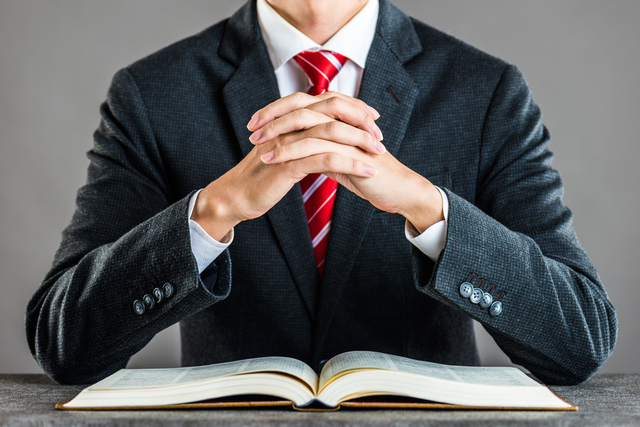
解約返戻金の金額が20万円を超す保険ですとか、20万を超す価値がある車を維持したい場合は、
相当金額を現金や新得財産から捻出して管財人に引き継ぐことで維持できるケースがあります。
⑴ 高額な解約返戻金
例えば、解約返戻金額が40万円のの生命保険があるとします。前述の維持できる基準である20万円を超しますので、原則は処分対象です。ただ、生命保険契約をいったん解約して、再度入りなおすとなると保険料が上がってしまうなどの弊害がありますよね。そこで、破産管財人に対し、自由財産から40万円を管財人に引き継ぐことで、当該生命保険の解約返戻金を放棄してもらい保険契約を継続できるといった可能性もあります。破産管財人に相談しましょう。
⑵ 高額な退職金
生命保険に次いで多いのが対象金です。退職金の8分の1の金額が20万円を超すことは多々あります。しかし、退職金は実際に退職しないと支給されません。かといって、裁判所や破産管財人が破産する方に対し、会社を退職するようにと迫ることも出来ません。
そこで、退職金の8分の1の金額を管財に引き継ぎ、それをもって退職金債権を放棄してもらうことになります。
当事務所で扱った案件では、退職金の8分の1の金額が90万円ほどあり、開始決定後に毎月分割で金銭を1年間くらいかけて積み立てて破産管財人に引き継いだというものがありました。
⑶ 第三者からの援助金の注意点
管財人に引き継ぐ金銭について、破産する方本人に資力がない場合は、親族からの援助金で対応することが可能です。
ただし、注意点としては、前述の破産開始決定の前に、親族から援助金が預金口座に振り込まれた場合、
それは破産手続での処分対象財産となってしまうということです。
ですから、援助を受けるのであれば、開始決定日の後に得るようにしましょう。
まとめ

自己破産手続をしても、全ての財産が処分されるわけではなく、生活に支障が生じないように一定の範囲の財産を維持することが認められています。
当事務所で扱う案件でも、何も処分されないで終わるという事件が多数あります。
当事務所では、自己破産手続きを積極的に取り扱っています。
初回の相談料は無料です。
自己破産・個人再生事件を300件以上解決してきた弁護士が対応します。
弁護士費用の分割払いにも対応しています。
相談は事前予約制です。問い合わせフォームからお問い合わせいただき、ご相談日の予約をお取りください。
【関連記事】
・自己破産とはどのような手続か
・自己破産による年金への影響と退職金との違い
