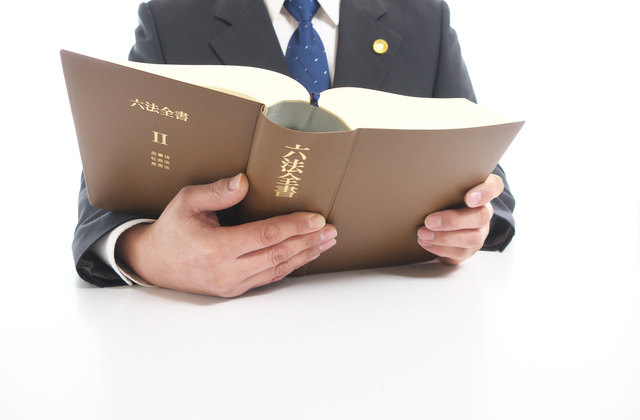交通事故による骨折 慰謝料、後遺障害、治療方法について

 |
東京都墨田区の錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。 |
交通事故で骨折された場合の治療の受け方や認められ得る後遺障害について解説いたします。
1.事故直後の対応
交通事故被害に遭い、骨折が疑われる場合には、直ちに整形外科に行きましょう。
レントゲン撮影やCTによる画像撮影をしてもらい、骨折の有無を確認し、骨折がある場合には、その証拠として残しておく必要があるのです。
事故後しばらく経っても痛みが引かないために、整形外科に行ってレントゲン等の撮影をしてもらう方がたまにいらっしゃいます。しかし、事故後から期間が空いていると、事故と怪我との因果関係が怪しくなってしまいマイナスに働く可能性があります。
そうなると、後々の後遺障害の認定にも影響します。
ですから、痛みがあるのであれば、念のため整形外科にてレントゲンやCTの撮影をしてもらうことをお勧めします。
2.治療法と通院期間

骨折の場合の治療方法は、ギブスを付けて固定し自然に骨がくっつくのを待つ保存療法と、外科手術を行う方法の大きく二つの方法があります。
骨折の際に骨折部分の骨がずれてしまうとそのまま固定しているとずれたままくっついてしまうため手術を行う必要があります。外科手術を行うような場合は、複数回の手術を行うケースもあります。
ギブスで固定する保存療法の場合、症状固定まで3か月から6か月程度であることが多いです。一方、外科手術を要する場合には、症状が固定するまで6か月超す長期間となることがあります。
症状固定となりますと、これ以上治療を継続しても症状が改善されませんので、後遺症が残る場合には、後遺障害の認定を受け、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求していくことになります。
3.骨折で認められ得る後遺障害
⑴ 欠損障害
欠損障害というのは、腕や脚の全て、または一部を失う障害です。
どの部分がどれくらい失われたかによって後遺障害等級が異なってきます。
⑵ 機能障害
関節が動かなくなる、動きにくくなるといった場合の後遺障害です。
どの程度の可動域制限があるかによって後遺障害等級が異なってきます。
⑶ 短縮障害
脚の長さが正常な状態のときよりも短縮する後遺障害です。脚の長さが変わることで歩行等に支障が生じます。短縮の程度によって後遺障害等級が異なってきます。
⑷ 変形障害
骨折した骨が正常の形とは異なった形でくっついた場合、または骨折部分がくっつかないまたはくっつく過程が停止することで本来曲がってはいけないところで曲がるといった場合の後遺障害です。前者は変形治癒、後者は偽関節と呼ばれます。
⑸ 神経障害
骨がくっついた後でも、骨癒合に不良がある場合や間接内を骨折した場合には、痛みが残ることがります。神経障害として後遺障害の等級でいうと12級または14級が認められる可能性があります。
後遺障害の認定がなされますと、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求することが可能となります。
4.まとめ

交通事故により骨折が疑われる場合には、早期に整形外科を受診しレントゲンやCTの撮影をしておきましょう。また、骨がくっついても痛みが残っていたり、骨折部分の周辺の可動域が制限されている場合には、後遺障害の認定がされる可能性があります。
弁護士に早めにご相談されることをお勧めします。
当事務所では交通事故案件を積極的に取り扱っています。
初回は無料相談を承っています。
お気軽にご相談ください。
リモートによる相談も対応しております。
相談は事前予約制です。問い合わせフォームからお問い合わせいただき、ご相談日の予約をお取りください。
【関連記事】