【不倫(不貞行為)慰謝料の求償権】放棄のメリット

 |
東京都墨田区の錦糸町駅そばの鈴木淳也総合法律事務所です。 |
不倫の慰謝料請求で問題となるのが「求償権」です。
求償権とは何なのか、求償権行為の流れや求償権を放棄する場合について具体例を交えながら解説します。
目次
不倫の慰謝料請求の法的根拠
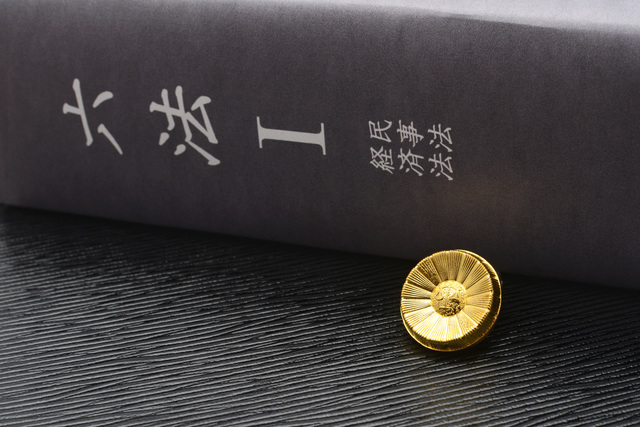
求償権が何なのかを理解するためには、まずは、不倫の慰謝料請求が認められる法的な根拠を確認する必要があります。
不倫の慰謝料請求は、民法709条の不法行為を根拠としています。
民法第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
既婚者であることを知っていて、または知らなかったことに過失があった状況で、不貞行為をして、配偶者の権利を侵害したということです。
そして、二人以上の者が共同して不法行為を行う場合は、共同不法行為となります。
民法第719条
数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
「不倫」というのは、不倫相手と共同して配偶者の権利を侵害するものです。
つまり、不倫は、共同不法行為ということになります。
共同不法行為となりますので、不倫した二人は、各自が連帯して慰謝料を支払うこととなります。
不倫された配偶者は、この二人のどちらに慰謝料請求しても構いません。
それぞれが全額を支払う義務を負うのですが、二人の間には負担割合というものが存在します。
ただし、注意が必要なのは、慰謝料の二重取りは出来ないということです。
なぜならば、不倫された配偶者の損害というのは、一つしかないため、二人のうちの一方から十分な慰謝料の支払いを受けた場合は、
損害が賠償されたことになるからです。
求償権とは

このように、不倫された配偶者は、自分の配偶者、その不倫相手のどちらに慰謝料請求してもいいわけです。
一般的には、離婚しない夫婦の場合、慰謝料請求するのは、不倫相手の方に行っていきます。
不倫相手としては、なぜ自分だけ金銭を払わなければならないのか、という思いになります。そもそも、二人で共同して不倫をしているわけなのだから、自分だけが悪いわけではない。二人に責任があるということです。
この責任については、両者でどちらがどれくらい悪いのかという責任割合(負担割合)というものが考えることになります。
ようやくここで、「求償権」とは何のか?
それは、慰謝料を請求された一方が慰謝料を支払った場合に、自分の責任割合を超える金額について他方に請求できる権利のことです。
分かりにくいので具体例を用いて説明します。
具体例
A(妻)とB(夫)は夫婦です。BがCと不倫をしており、それをAが知るに至りました。Aとしては、Bが謝罪していることから離婚までは考えていません。ただ、Cのことがどうしても許せないため、Cにだけ慰謝料100万円を請求しました。そうしたところ、Cは100万円をAに支払いました。CはBに対して何か請求できないでしょうか。
この場合、BとCは共同不法行為が成立します。AはBとCどちらにも慰謝料請求出来ます。CがAに100万円支払ったことから、Aの損害は賠償されたことになります。
そして、Cは、求償権を行使して、Bに対して責任割合に応じた金額を請求することが可能です。
BとCの責任割合を仮に6:4だとしますと、Cの負担する部分は40万円ということです。そこで、CはBに対し、100万円からCの負担部分の40万円を差し引いた60万円を請求することが出来ます。
不倫の責任割合
以上のとおり、求償権の行使においては、責任割合が重要となってきます。
不倫の慰謝料が問題となる場面で、責任割合は、不倫をした配偶者の方が不倫相手よりも重くなると考えられています。
それに加えて、個別の事情によって判断していくこととなります。
個別事情には以下のようなものがあります。
・不倫相手が職務上の地位を利用して不倫関係を強要した
・不倫関係の解消を一方が求めていたのに他方が応じなかった
・離婚するから関係を続けて欲しいなどと関係継続を求めていた
ただし、責任割合について当事者間で合意できない場合は、裁判所に決めてもらうことになります。
求償権の放棄

設例
A(妻)は、B(夫)とCが不倫していたため、Cに慰謝料請求をしCから100万円を受けとった。
そうしたところ、CはBに対し、求償金として50万円を請求してきた。
設例のように、求償権の行使とは、一般的には、慰謝料の支払いを終えた後に、不倫相手に対し金銭の支払をすることになります。
ここで、AとBが①離婚する場合、②離婚しない場合を考えてみましょう。
①離婚する場合
Aとしては、Bと離婚しますので、Bが求償金の請求を受けようが受けまいが関係がないと言えます。
CがBと連絡を取ることも特に気にしないかと思います。
②離婚しない場合
Aとしては、Bと離婚しませんので、Bが求償金の請求を受けると、同じ家計の財布からCへ金銭を支払うことになります。
いわば、Cから受け取った金銭の一部をCに戻すようなものです。
また、求償金の請求とはいえ、CがBに連絡を取ることも心情的には抵抗があるかもしれません。
既に解決した問題を蒸し返される思いかもしれません。
このように、離婚する場合はいいのですが、離婚しない場合に求償権の行使をされると嫌だと思われる方もいます。
そのような場合に、 不倫の慰謝料の協議の中で、「求償権の放棄」を選択することがあります。
合意書の中に、求償権を放棄する条項をいれるのです。
ただ、求償権を放棄するということは設例の場合、Cだけが責任を負うことになってしまうため、Cとしては簡単に放棄することに応じるわけがありません。
そこで、 Aとしては、慰謝料の金額を求償金に相当する額だけで減額することで、Cに放棄してもらうという流れになってきます。
設例の場合でいえば、Aは、Cが求償権を放棄するという条件で慰謝料を50万円とすることに合意することとなります。
CとしてもBに対し求償金を請求する手間が省けるというメリットがあります。実際問題、Bが払ってくれるという保証もありません。
払わなければ裁判を起こさなければならないのです。
以上のように、当事者それぞれの利害関係に基づいて、求償権が放棄される場合があるのです。
求償権を行使する流れ

不倫の慰謝料請求をされてから、求償権を行使するまでの流れは以下のとおりです。
不倫の慰謝料請求をされる
↓ 弁護士に対応を依頼
慰謝料の協議の中で、求償権を放棄するか否かについても協議
↓
取り決めた不倫の慰謝料の支払いをする
↓求償権の放棄なしの場合
不倫相手に求償金を請求する
↓
不倫相手と責任割合について協議する
↓
不倫相手から求償金を支払ってもらう
↓
求償金を支払う(支払った)旨の書面を取り交わす
求償権に関するご相談は男女問題を得意とする当事務所へ

以上のとおり、求償権については、不倫の慰謝料の協議の段階でまず問題となります。
そのため、不倫の慰謝料の段階で弁護士を付けて、検討するのがいいでしょう。
当事務所では不倫の慰謝料請求の対応をご依頼されたお客様から求償金の請求に関するご依頼も多数いただいております。
当事務所で解決した事案の多くは、裁判までいかず任意交渉で解決できております。初回は無料相談となります。
電話による相談も可能で、遠方にお住まいの方からの依頼も承っております。
ご相談は事前予約制です。問い合わせフォームからお問い合わせいただき、面談の予約をお取りください。
【関連記事】
・不倫相手の名前がわからなくても、慰謝料請求できるのか
・【不貞行為】ダブル不倫の場合の慰謝料の決め方。ゼロ和解という方法
求償権放棄による慰謝料の解決事例
1 女性 求償権放棄を前提に慰謝料を大幅に減額
 |
職場が同じ既婚の同僚男性から執拗に誘われた結果、不倫をしてしまい、交際男性の妻が依頼した弁護士から慰謝料300万円を請求する内容証明が届き、困惑して当事務所にご依頼されました。
慰謝料としては80万円程度が妥当な事案でした。相手方は金額には同意したものの求償権の放棄を求めてきました。相手方は求償権を放棄する前提で半額の40万円と主張してきましたが、相手の責任割合の方が重い事案であったことから、こちらの責任割合は3~4割であることを主張し、最終的に求償権放棄する代わりに慰謝料30万円で和解することが出来ました。 求償権を放棄することで、支払う慰謝料自体を大幅に減額できた事案です。
|
